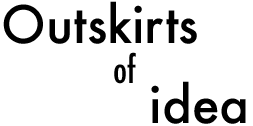茅野のダイヤ菊の件を読んでいて、触発された。
~長野県ダイヤ菊酒造4代目蔵元・宮坂氏「小津先生が飲んでいたと思われるのは昭和30年代当時の特級か1級。特級のダイヤ菊だと米も6割程に削っていたはずです。最近、昭和5年に撮影された酒蔵のフィルムが出てきたのですが、中に”精白度”(米を削った数値)5割以上という高雅芳醇の良酒”という書き込みがありました。つまりその頃から米を削るといい酒ができるというのは知っていて、実践したのがダイヤ菊です」
近くの酒を扱う深夜のコンビ二には、ダイヤ菊はなかった。仕方がないので月桂冠「月」に甘んじて、肴に鰊の酢漬けを買う。帰り道、小津の蓼科での酒盛りが勝手に浮かんで、酒は、短い限られた決定を決心させる為の、環境作りということだぜと、わかった気になっていた。
深夜の熱燗と、鰊の酢漬けはだまされているとしても、旨い。
今回フィルムからDVD化させたイマジカの井関修氏と小津の助手だった川又昂氏との対談の中で、テープへの変換から開放されて、mpeg圧縮でのDVDコンバートの技術的進化は理解できたが、むしろそれよりも、やはり当時は赤を選んでコダック、空の青を避けてアグファという選択肢で行ったフィルム撮影と、「麦秋」「東京物語」の白黒の美しさを繰り返す彼らの、オリジナルテキスト至上主義が頗る気に入って、二本目の燗つけをした。(錫のちろりと燗は55度という件ににココロを奪われる。探そう。誰か知っていたら教えて頂戴)
いつだったか白岡順の白黒写真の、あるいはまた霧のようなアウトフォーカスを好んだ時があった。今は、例えば次女の書いてくる拙い書道のような鮮明な黒と、ほんの少しの滲みが好ましい