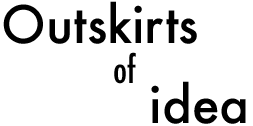このところ時間がとれなかったが、ようやく深夜TimeLine、日曜日の恋人たちを観る。月末あたりにレンタルリリースされるアドルフの画集と殺人の追憶の予告に誘われる。
次女が遊んでいるドンキーコング2(GBA)をちょっとやるとむつかしい。トイレに座って新しいFFTをはじめるが、GBAの画面が小さいので目が痛い。システムは洗練している。
8/20に次女の診察の予約をとる。
日常の反射や平常の知覚レベルではない、作品化された言葉と映像の落差を感じることが、最近個人的に面白い。言葉には文体というものがあって、これがオリジナルティーともなるが、新聞や雑誌などの状況記述でさえ、記述した人間のどこか恣意的なレトリックが鏤められ、 鳥瞰の眺めと同質の言葉となると、なかなかみつからない。過去を記述する際には、この世界に関与せずに傍観するような言葉となるけれども、現在をそれに似た傍観あるいは厭世(逆でもいいが)で記述すると、死者の物言いになるらしい。これはつまり生きている人間ならば、傍観という客観は土台無理であることを意味するが、気分としては、言葉を綴り重ねる反復は、自然と死を呼ぶものだ。 一度きりの固有な発作的な呟きは、転がっていってしまうけれども、重なる呟きは、互いに錯綜して墓をつくるように強情に、予想や計画を裏切る構築を勝手にしてしまうものだ。映像は、実際に知覚する視覚視野の擬態だから、眺めの体感はもとより喪失している。顎をずらして眺める二つの目玉が捉える空間は、映像表現では本質的には再現できない。我々はこの擬態の提供する情報から得られる想像力に慣れてしまっているわけだが、映像の力はその慣れた姿よりも、平面映像の持つ「詩的」な広がりの獲得を指向している。この場合の詩的というとき言葉は排除される傾向がある。
茶番を役者の名前でカバーしたSphereを娘らと観る。モノリスの焼きなおし。こうした作品は、無名の役者を使うべきだ。つづけてcity of god。来週は少し構想の時間ができる。