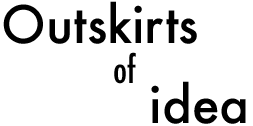眠れなくなっていたので、熟睡を呼び込むために、ファーゴと鏡を観る。このふたつを選ぶのに随分時間がかかった。選択の力が萎えていること自体、覚醒と眠りの中間に漂っていることを意味していると思った。どちらも一度再生を停止させてしまっていた。観ることへ魂を注ぐ事ができない。肉体の疲労は無いが、魂が疲弊しているということだ。
こうも同じ作品を違った感触で取り込むことができるのは、つまり作品の力だが、ファーゴは、出来事の偶然で唐突な連携を物語の必然とさせた手法だけで、俳優の意味が浮き上がってしまった。こうした事実を物語にする時、忠実な再現には、暗闇がわけのわからないまま放られていないと茶番になる。鏡は以前から感じていた複雑に平行してあるメタファーが、更に複雑に読み込まれて、短い作品だが、その何倍もの超代な叙事詩を眺めているような緊張が率直な疲れを与えてくれる。一体どのような編集が行われたのだろうか。ひとつひとつのパンやカットの時間を計りたくなる。鏡の本を取り出していた。
自身の記憶を構築するというのは、虚飾を剥ぐだけで大変な作業だが、ありのままという固まりとして差し出す作業は、途方も無いことだ。対象世界と文脈を注視する「水の机」もゆっくりと行うほうがいいだろう。吟味することが楽しさと喜びになればいい。ぬいぐるみ。素足の汚れ。寝顔。広角レンズ。ささやき。鉛筆と消しゴム。午前中のコップ。レンジファイダーのフィルム面とレンズとの距離。ウイスキー。